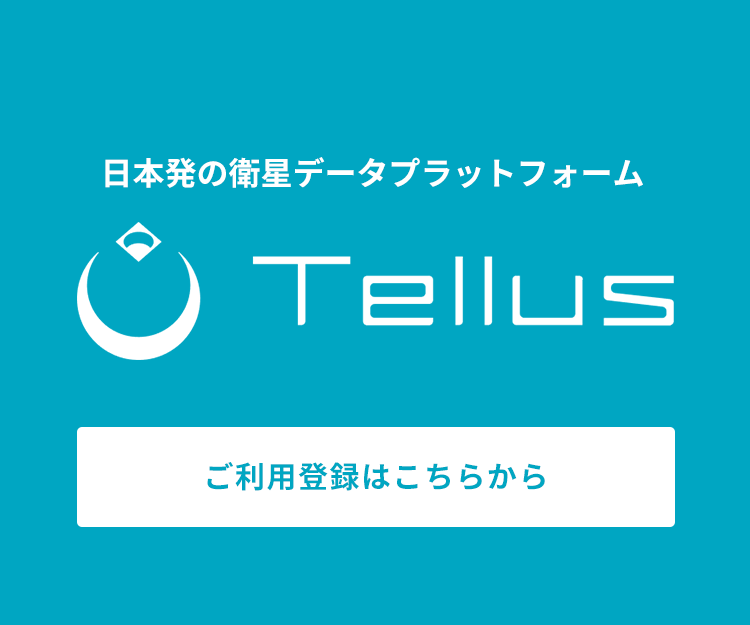「人類の可能性を拡げ続ける」「スタートアップの勝ち筋はスピード」5周年を迎えたPale Blueの手応えと展望
安全で持続可能な「水」を用いた推進機開発をし、すでに宇宙空間での実績もある宇宙ベンチャーPale Blueの創業者である浅川純さんに、創業から5年間という宇宙開発としては決して長くない期間に実績を積み重ねたその歩みと、これから目指す未来について伺いました。
創業から5年を迎えたPale Blueは、安全で持続可能な「水」を用いた推進機開発をし、すでに宇宙空間での実績もある宇宙ベンチャーです。大学発の研究シーズを出発点に、宇宙空間における“モビリティ”の可能性を広げる存在として注目を集めています。
製品化から量産、そしてグローバル展開までを見据え、Pale Blueの挑戦はますます加速し拡大することが期待されます。5年間という宇宙開発としては決して長くない期間に実績を積み重ねたその歩みと、これから目指す未来について、創業者の浅川純さんにお話を伺いました。

創業のきっかけは基礎研究と実利用のギャップ
宙畑:まずは、浅川さんが起業することを考えたきっかけから教えていただけますか?
浅川:大学院生のときに関わっていた小型衛星プロジェクトが大きな転機でした。私が所属していた小泉研究室で推進機をつくり、それを中須賀・船瀬研究室が製作した衛星に載せる、という共同プロジェクトだったんです。基礎研究だけをしていたときには見えなかった「実利用」の厳しさに直面しました。
宙畑:具体的にはどんな違いを感じたのでしょうか?
浅川:例えば、振動試験ですね。研究では「推進性能や推進機内部の物理現象の解明」が主なテーマなので、振動に耐えるかどうかはあまり考えません。でも、実際に衛星に載せて打ち上げるには、振動試験に絶対合格しなければならない。使う側からすると推進機内部の物理現象よりも、衛星に搭載して使用するうえで必要な要求を満たしているかが重要。それに対して研究者側は「どんな物理現象で推力が出ているのか」に関心がある。この視点のズレに気づいたのが、最初の大きな発見でした。
宙畑:そこからプログラムに参加することで会社を立ち上げようと思われたのでしょうか。
浅川:最初から「会社を作ろう!」と決めていたわけではありません。私と同期であり、Pale Blueの共同創業者でもある柳沼と2人で、「アントレプレナー道場」という東京大学の起業やスタートアップを一から体系的に学ぶプログラムに参加したのが始まりでした。博士課程1年のときですね。
宇宙ベンチャー起業家の先輩方が道場の卒業生で、直接話を聞く機会があり「すごくいいよ」と勧められました。また、その年から単位が取得できるようになったんです。「じゃあ試しに行ってみようかな」と。
宙畑:その経験から起業すると決めたきっかけになったのですね。
浅川:そうですね。アントレプレナー道場は3段階あって、初級では先輩起業家の講演を聞き、中級ではより実践的な授業、そして上級では自分たちで事業計画を作るところまで行きました。そこで初めて「水推進機を事業にできないか」と考え始めたんです。
創業時は、小泉先生ともう1名、同じく小泉研究室の中川が加わる形で4人でした。
宙畑:それが今や5年で50名以上の社員数となり、10倍以上に規模が拡大したのですね。
なぜ“水推進”なのか? そしてどう実現したのか
宙畑:「水推進機」の事業化に踏み切るきっかけは何だったのでしょうか?
浅川:学生時代にいくつかの小型衛星のプロジェクトや宇宙開発のカンファレンスに参加するなかで、「小型衛星ミッションを成立させるには推進機が必要不可欠だ」と実感したのが最初の気づきでした。その後、アメリカのユタ州で毎年開催されるSmall Satellite Conferenceにも参加し、海外の企業が推進機を軸に衛星メーカーと商談している現場を見て、「これは事業としても成り立つんだ」と肌で感じました。

宙畑:すでにヒドラジンやキセノンといった他の推進剤も選択肢としてあるなかで、なぜ“水推進機”に取り組んだのか、理由を教えてください。
浅川:小泉研究室に入った当初は水の研究グループはまだ始まっていなくて、私自身もキセノンを使った推進機の開発に関わっていました。ただ、開発はもちろんのこと「安全審査」や「ドキュメントの整備」が非常に大変で、衛星に載せるまでのプロセスに苦労したんです。また、キセノンは希少なガスで、地球上での採取量にも限界があるんです。「このままではビジネスとしてスケールしないな」と感じました。
宙畑:キセノンはそんなに希少なんですね。
浅川:そうなんです。大気中に含まれる割合も非常に低く、酸素や窒素を生成する過程で副産物的に取れる程度。人工的に合成できるわけでもなく、自然界に存在するものを抽出するしかありません。そのため、調達も難しいし、推進剤として使い続けるには不安がありました。一方で、水は圧倒的に安全で、手に入れる難易度も高くありません。将来的に小型衛星の打ち上げがさらに増えていく中で、「持続可能な推進剤」として水が最も適していると判断しました。
宙畑:事業としても、今後の展望を考えても、水を利用した推進機は理にかなっていたと。
浅川:はい。ただし、技術的に簡単かというとそうではなくて。水推進の技術は小泉研究室で長年積み重ねてきた推進機に関する研究成果があったからこそ、実現できた部分が大きいです。
また、小型衛星が世界的に増え始めたこの数年で、水推進というソリューションが求められたのは絶好のタイミングだったと思います。
Pale Blueの製品ラインナップとこれから
宙畑:現在、Pale Blueさんではいくつかの水推進製品を展開されているかと思います。まずは今のラインナップについて教えてください。
浅川:現在は主に3種類の水推進機をラインナップしています。すでに事業化しているのがPBRというモデルで、これは小型衛星向けの実用機としてすでに複数台が宇宙で稼働実績を積んでいます。そして次に控えているのがPBIです。こちらは2025年度の本格導入を目指していて、すでに開発は完了。イタリアのD-Orbitの小型衛星「ION Satellite Carrier」に搭載して2025年に2回打ち上げることを2025年1月に発表しました。
さらに、水ホールスラスタの開発も進行中で、これが加われば、さらに幅広い用途に対応できる体制が整います。

宙畑:PBRはすでに実用化されたとのことですが、事業化にあたって特に苦労された技術的なポイントはありましたか?
浅川:大学時代の研究段階で得られた知見を、実際に衛星に搭載可能な製品にまで落とし込むのは、やはり大変でした。特に苦労したのは、非常にコンパクトな筐体に必要な機能をすべて詰め込むことです。例えば、流体制御だけでなく、電気的な制御基板やソフトウェアのアルゴリズムまで、すべてを一つのパッケージとして成立させる必要がありました。
宙畑:元々の研究メンバーだけでは技術的に難しかったこともあったのではないでしょうか?
浅川:実は、最初の正社員として採用したのは、宇宙分野の経験者ではなく、電気系のエンジニアでした。電気系を専門とするエンジニアの加入が非常に大きく、推進機を「一つの製品」として完成させる上で、研究室にはなかった視点やノウハウを持ち込んでもらえたのは非常に大きかったです。出資してくださったベンチャーキャピタルのご縁でつながったのですが、本当にありがたい出会いでした。
「研究から製品、製品から事業へ」宇宙での実績が顧客からの信頼を得た、Pale Blueの5年間
宙畑:大学での研究から実用レベルの製品にするまでには、相当なギャップがあったのではないかと思います。最初の設計や製品化にはどのように取り組まれたのでしょうか?
浅川:大学時代のプロトタイプの設計ももちろん使ってはいたんですが、あくまで研究レベルのものでしかなかったので、実用化に向けては設計を見直して、図面も引き直しました。
ただ、それだけでは製品とは呼べません。特に「量産」できるものにするという点では、もう一段のハードルがありました。
宙畑:量産という観点で具体的にどのようなハードルがあったのでしょうか?
浅川:量産化するということはつまり、「誰が作っても、同じものが、同じスペックでできる」状態にする必要があります。また、研究と違って、製品のスペックだけでなく、お客様が求めるコストや納期にも応える必要があります。そのためには、属人性を排除して、再現性のある製造プロセスをつくることが必須でした。
宙畑:創業当初は、属人的な工程が多かったということですね。
浅川:創業初期は、組み立ても試験も「この人しかできない」というような工程があり、創業メンバーでなければ扱えない、ということも少なくありませんでした。試験プロセスも暗黙知の塊みたいなところがあって、これでは量産はできないというのが課題でした。
その上で、2023年1月に打ち上げられたソニー社の衛星に我々の推進機が搭載され、実際に宇宙空間でしっかり動作したというのは非常に大きな転機でした。その時点でチームは30人以上の規模になっていて、ようやく「製品」として事業化ができると実感できるタイミングでした。

宙畑: 宇宙での実績が与えるインパクトは大きいんですね。
浅川:そうですね。お客様に製品を説明する際には、 短時間であっても「宇宙で動いた」という事実があるだけで信頼が大きく変わりますし、ソニー社のように打ち上げてから2年が経過しても安定して動作している実績は、さらに大きな信頼につながります。
宙畑:今、製品としては複数展開されていますが、それぞれの特徴やお客様の反応はいかがですか?
浅川:現在は主にPBRとPBIという2種類の水推進機を展開しています。たとえばPBR-10やPBR-20はコンパクトで低電力の衛星を扱うお客様に好まれています。一方でPBIはより長時間の推進ができるモデルで、衛星の寿命を伸ばしたいというニーズに応えています。どちらにも共通するのが「水」の安全性と扱いやすさに対する評価ですね。
宙畑: 市場からの反応や海外との関係構築についても、ここ1〜2年で変化があったのではないでしょうか?
浅川: そうですね。最近では展示会などで「Pale Blue 知ってるよ、水推進の会社でしょ」と声をかけていただけることも増えてきて、認知度は確実に上がってきています。海外メディアに取り上げていただいた影響もあると思いますし、たとえばD-Orbit社のような海外の企業と、実証パートナーとして自然な形で連携が始まるケースも出てきました。展示会やカンファレンスでの出会いが大きなきっかけになることは、やはり多いですね。
宙畑:登壇や展示会などで、伝える内容として意識されていることはありますか?
浅川:やはり「宇宙実績」が一番大きなアピールポイントです。そして、今後の予定や「生産体制」についても話せるようになってきたので、そこも強みとしてしっかり伝えるようにしています。実証だけでなく、それを支える仕組みも見せられることで、さらに信頼を得られると思っています。
スタートアップがグローバル市場で勝ち切るためにはスピードが重要
宙畑:Pale Blueは創業から5年という期間で実証も成功し、海外のパートナーとの連携も進められていて、非常にスピード感のある展開だと感じています。浅川さん自身はこのスピードについてどのように見ていますか?
浅川:正直、もっと早くしたいというのが本音です。大学にあった技術シーズを起点にできたのは大きなアドバンテージでしたが、海外には我々より数年早く創業し、先行している競合もいます。

浅川:現在は、国内外での宇宙作動実績をさらに増やしていくと同時に、生産体制の強化にも着手しています。つくば市に生産技術開発拠点を立ち上げ中で、今後はそこを軸に本格的な生産体制を整える予定です。そのため、製造部門の人材も積極的に採用中です。特に工業製品としてのQCD(品質・コスト・納期)をしっかり満たす体制が必要だと思っています。
宙畑:拡大をするうえで課題と感じられていることはありますか?
浅川:現在、正社員で約50名、役員なども含めて60名ほどです。今後さらに拡大していく予定ですが、人数が増えるとどうしても鈍化してしまう側面も一部あるので、組織の拡大と共にどうスピードを維持・向上するかが大きなチャレンジです。
宙畑:やはりスピードがスタートアップの価値だと?
浅川:はい。スタートアップが大企業に勝てる要素は「スピード」だと本気で思っています。資本力では敵わない。ならば、誰よりも早く試して、実証して、改善していく。その繰り返ししかないです。
宙畑:日本の宇宙産業が世界と渡り合うために、今後必要なものは何だと思いますか?
浅川:スピード、そして実証を重ねる機会、そして事業としての再現性。この3つをしっかりと組み合わせて取り組んでいくことが必要だと思います。日本は政府やJAXAなどの支援も手厚いので、そこを活かしながら、グローバル市場で勝てる日本発の宇宙スタートアップを増やしていきたいですね。
宙畑:宇宙実証の実績が信頼につながり、機能検証以上の効果があるということですね。
浅川:そうですね。たとえば先に述べたソニー社の人工衛星の実証で、2年経っても安定して稼働している事例ができたことで、世界の見方が変わったと実感しています。実際に国内外で受注も増えていますし、やはり実証の力は大きいです。
「最初は”幸福の最大化”と言っていた」今のミッション「人類の可能性を拡げ続ける」に込めた思いと理想の姿
宙畑:この5年を振り返って、特に印象深かったことはありますか?
浅川:やっぱり、初めて推進機が宇宙で動いたときですね。バルブが開いて、水が流れて、データが届いた瞬間の感動は忘れられません。
宙畑:ありがとうございます。これまでPale Blueさんの現在地について伺ってきましたが、ここからは少し未来の話をお聞きしたいと思います。まず、「人類の可能性を拡げ続ける」というミッションに込めた思いについて改めて教えてください。
浅川:創業当初、私がよく使っていた言葉は「科学技術で人類の幸福を最大化する」でした。ただ、幸福って人によって定義が違うので、もっと本質的にどうあるべきかと考え続けた結果、「可能性」に行き着きました。目の前の課題に対して、選択肢が多ければ多いほど、人はより豊かになれる。その選択肢を科学技術の力で増やし、持続的に提供していくという意味で「人類の可能性を拡げ続ける」という言葉に落ち着きました。
宙畑:「宇宙」や「水推進」という言葉がミッションに入っていないのは何か意味があるのでしょうか?
浅川:はい。宇宙に限らず、私たちの活動の本質は課題を解決し、未来の可能性を拡げることだと考えています。たまたま今は、宇宙というフィールドにおいて水推進技術を軸に事業を展開していますが、将来は他の課題に挑んでいるかもしれません。
また、我々が提供している推進機は、単なる「部品」ではなく、宇宙空間における「動く能力」——つまりモビリティを提供するものです。今は推進機をハードウェアとして提供していますが、将来的には推進をサービスとして提供する方向にも広げていきたい。いわば、宇宙空間のモビリティ・インフラを担う存在を目指しています。
宙畑:将来的には、衛星だけでなく構造物やサービスそのものを提供していく可能性もありますか?例えば、宇宙空間に水を補給する「ガソリンスタンド」のようなインフラの構築などもありえるのでしょうか?
浅川:そうですね。推進機に限らない開発も視野に入れています。また、D-Orbitやブルーオリジンが展開しているようなモビリティサービス型の事業モデルも意識しています。
宙畑:水という推進剤にこだわりすぎない姿勢も、その先を見据えているからこそなんですね。
浅川:そうですね。今は水がベストだと考えていますが、将来的に別のものが最適なら、そちらを選ぶべきだと考えています。現在は、技術的に水推進に強みを持ち、そのニーズがあると考えているからこそ、そこに集中していますが、技術やニーズが変われば我々も柔軟に変化していきます。
読者へのメッセージ:これから、宇宙ビジネスに挑戦する人たちへ
宙畑:最後に、これから宇宙産業に参入しようとする企業や、浅川さんのように大学から研究を続けてきて事業化を目指す方々に向けて、アドバイスをいただけますか?
浅川:何か少しでも興味があるなら、やるべきかなと思っています。世の中のニーズとしても、宇宙産業・宇宙利用の必要性は間違いなくあると思っています。さまざまな観点からその重要性が語られていて、一つの大きな流れがあるのは確かです。
ただ、時代の流れ、社会の流れとしても宇宙領域は必要とされている一方で、事業として成立しきっているとは言い難く、成熟していない、成長フェーズの産業です。
まだ「こうやれば絶対に事業として成功する」といった正解が見えているわけではない。見方を変えれば、だからこそ、非常に面白い環境で、実行する人が一番になれる状態だと思います。
宙畑:実際に飛び込んでみて、「ここは気をつけた方がいい」と思うことはありますか?
浅川:やはりどうしてもお金と時間はかかります。これはある程度覚悟が必要だと思います。ハードウェアが絡むと特にそうで、目の前で作ったものが翌月には世に出る、みたいな世界ではないですし、そういった意味ではちょっと特殊な業界かなと思います。
宙畑:ありがとうございます。最後に、5周年を迎えた今、社内の皆さんや関係者の方々に向けてのメッセージがあればお願いします。
浅川:この5年は本当に、みんなで大変な中を乗り越えてきた時間だったと思っています。プロダクトがない中からまずは作って、それを売りながら、必要な資金やリソースを集めて、とにかく走り続けてきた。苦しみながらも前に進んできた5年間でした。
その積み重ねが、少しずつ花開き始めていると感じていますし、社員もそう感じてくれているのではないかと思います。宇宙作動の実績もいくつか出てきて、生産体制の構築にも取り組んで、国内外から受注も増えてきた。製品を作って出荷する——そんな「事業としての活動」が着実に増えてきています。
今はまだPBRが中心ですが、今年はPBIの実証も複数予定されています。これがうまくいけば、次のフェーズに進めると思いますし、水ホールスラスタの開発も仕込んでいます。まさに、次のステージに向けて会社全体が動き出している、そんなフェーズに入ってきていると思います。
編集後記
取材の中で特に印象的だったのは、創業者の浅川さんの「スピードこそがスタートアップの競争優位性」という言葉です。当初、Pale Blueが5年間で到達した宇宙実証や製品化のスピードの秘訣を伺おうと取材に臨んだのですが、当の本人はまだまだスピードが足りないと感じていた……その思いが、技術開発から製品化、そしてグローバル展開まで、驚くべきスピードで事業を推進できている要因なのでしょう。
今回の取材を通して、Pale Blueの設立から現在までの道のり、そしてこれから目指す未来について知ることができました。水推進という技術を基盤に、宇宙でのモビリティインフラを構築するという壮大なビジョンにあらためてPale Blueが拡げる人類の可能性が楽しみになりました。