「(最初は)儲かる匂いがしなかった」P&Gの経営管理から宇宙ビジネスに参入して気づいた宇宙という極限環境のポテンシャル
非宇宙業界から宇宙業界に転職をした人に焦点を当てたインタビュー連載「Why Space」、4人目のインタビュイーはSpace Food Lab.の取締役、浅野高光さんです。P&Gの経営管理部門でマーケットを大きくする感覚を身につけられた浅野さんが宇宙産業で見つけたビジネスチャンスとは?
非宇宙業界から宇宙業界に転職をした人に焦点を当てたインタビュー連載「Why Space~なぜあなたは宇宙業界へ?なぜ宇宙業界はこうなってる?~」に登場いただく4人目は、外資系消費財ブランドの大手P&Gの経営管理本部で市場動向を常に把握し、マーケティング部門とも連携しながらキャリアを積み、その後P&G時代の同期が立ち上げた企業に転職。事業を推進するなかで宇宙ビジネスに出会い、現在はSpace Food Lab.の取締役も務める浅野高光さんです。

本連載「Why Space」では、非宇宙業界から宇宙業界に転職もしくは参入された方に「なぜ宇宙業界に転職したのか」「宇宙業界に転職してなぜ?と思ったこと」という2つの「なぜ」を問い、宇宙業界で働くリアルをお届けしてまいります。
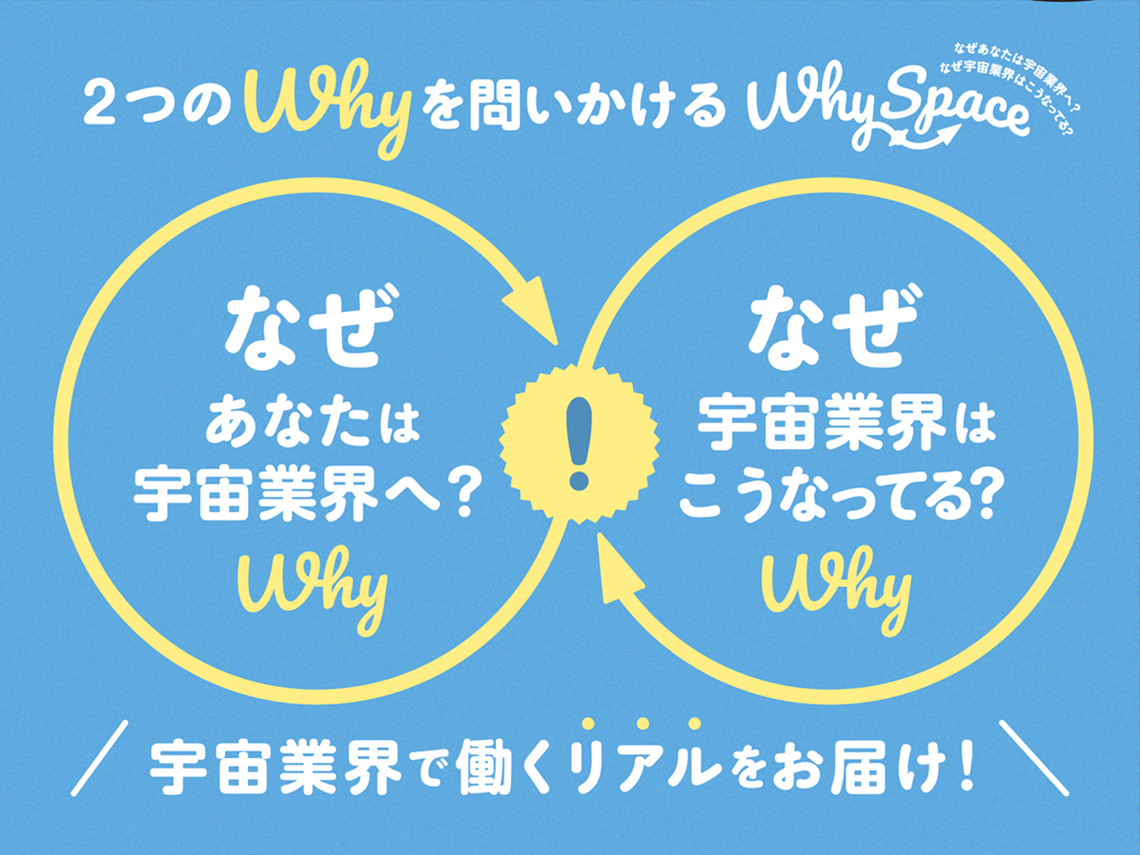
農学で「システムという捉え方」を学び、ミュージカル劇団とP&Gのインターンでビジネスを学んだ大学時代
宙畑:浅野さんは大学で農学部に進まれています。もともと食や農業に興味があったのでしょうか?
浅野:正直に言うと、最初から農学に強い興味を持っていたわけではありません。理系に進みたいとだけ漠然と考えていたのですが、工学や医学にはあまり興味が湧かず、もう少し身近に感じられるものを探していたところ、環境農業やバイオテクノロジーの分野には少しだけ興味もあり、農学部に進むことを決めました。典型的なお受験学生です笑
宙畑:農学部ではどのようなことを学ばれましたか?
浅野:農学は、細胞生物学のようなミクロな側面や(自然や人間の営みといった)環境の循環などのマクロな側面を学ぶ学問です。例えば、植物が光合成を行うときの炭素や窒素のメカニズムや流れを学び、加えて生態系の中でどういった形で物質が循環しているのかを理解します。この循環等の仕組みを学ぶ過程で、私は農学部がシステムや仕組み全体を理解するのに適した学部だと、今思い返すとそのように感じます。その理解と感覚の積み重ねにより、システム的な思考が磨かれたと感じています。
宙畑:農学からP&Gという流れは、少し変わったご経歴のように思ったのですが、どのような経緯があったのでしょうか?

浅野:大学時代は、ミュージカル劇団に所属しており、ミュージカルを通じて、単なるエンターテインメントの枠を超えて、ショービジネスの奥深さに魅了されました。ロンドンやニューヨークのショービジネスの現場を見て、日本でも劇団四季のようにビジネスとして成り立っている例を知りました。
その体験からビジネスが成り立つ理由や仕組みに関心を持ち、大学院1年生のときにP&Gのインターンシップに参加しました。これが最初のP&Gとの接点です。P&Gのインターンシップでは新商品としてどんな洗剤を市場に投入すべきかを検討し、マーケティングや消費者トレンドを考慮しながら経営戦略を立てるというケーススタディを行いました。ビジネスの力で何かを動かせることにとても魅力を感じました。
「インサイトをもとに事業の重要な意思決定をリードする」P&Gの経営管理で学んだ視点とマーケティングの面白さ
宙畑:P&Gというとマーケティングの職種が世間では有名な印象がありますが、浅野さんは経営管理本部に入社されています。経営管理とマーケティングはどのような役割の違いがあるのでしょうか?
浅野:マーケット情報や消費者トレンドから消費者ニーズを捉え、どんなお客様に、どのようなサービスや商品を、どのように伝え販売するのかを考えるのが一般的なマーケティングのアプローチです。一方で、経営管理本部の仕事は、マーケットがこれぐらいの大きさでこれぐらいのグロースのポテンシャルがあるんだったら、こういうところにこれぐらいのものを入れると、これぐらいのサイズ感でビジネスを作れる可能性があると見るアプローチをします。
宙畑:その違いがあるなかで、浅野さんが経営管理本部を選ばれた理由を教えていただけますか?
浅野:数字を扱い、マーケットポテンシャルを測り、勝負を仕掛けていくということは、かなり努力しなければ学べなさそうだなと思って当時経営管理本部の方を選びました。
宙畑:具体的には、どのような業務をされていたのでしょうか?
浅野:パンパースやジョイといった消費財のブランドを担当していました。P&Gでは経営管理の視点からマーケティングの考え方を学ぶ機会も多かったですね。
特にP&Gは「ヒューマンセンタード」なアプローチで、消費者のインサイトを深く掘り下げ、それに基づいて商品を開発します。日本の多くの会社は技術を基にした商品作りが主流ですが、P&Gではまず消費者の感情や行動からスタートするんです。
私は経営管理の担当でしたが、そうした調査手法に興味を持っていたので、上司からはなぜ?と言われることもありましたが、消費者調査に参加することもありました。
宙畑:経営管理とマーケティングの連携について、どちらの分析が先に入ってから動くなど、実際にはどのように進めていたのでしょうか?
浅野:両方が対等に業務を進めていましたね。まず、最も重要なこととして、一般的なことかとも思いますが中期経営計画において会社全体のビジネス成長の目標が設定されます。上場会社として株主に対しての価値を提供するため、(ベンチャーのように急激な成長が求められるということはなく)持続的に年数%の成長を続け、5年間でどれだけの売上増加を目指すかが定められます。その目標に向けて、マーケティング部門や経営管理部門を含む各事業部門が協力して戦略を策定します。
たとえば、あるブランドの売上を5年で100億円増やす目標がある場合、そのためにはどの消費者層にリーチするか、新たにどんな製品を投入するかなどを、主にマーケティング部と連携して検討します。マーケティングが新しいターゲット層を提案するときには、私たち経営管理部門がその提案が会社の長期戦略に沿っているかを評価し、場合によってはコスト面でもアドバイスをします。また競合分析を通じて競合他社がどういった層を狙っているかも考慮し、より効果的な市場戦略を作り上げるよう努めていました。
「儲かる匂いがしなかった」浅野さんが防災食市場を知り、宇宙食に可能性を見つけるまで
宙畑:P&Gから退職して新しい会社に転職することを決断されたきっかけについて教えてください。
浅野:それは、P&G時代の同期であり、今私が取締役を務めているエムエスディ、Space Food Lab.の代表である北島からの誘いが大きかったですね。彼は私より先にP&Gを辞めて、新しい大学院の設立支援や産学連携支援などに取り組むベンチャーを立ち上げ、教育・学修関連の事業に携わっていました。日本でも専門分野の融合が叫ばれ始め、複合型人材の育成が重要視されるようになっていた頃です。そんな教育・学修業界にもHuman Centeredにあたる学修者起点のニーズを感じて、教育の世界に飛び込むことを決意したんです。
宙畑:教育から宇宙食にはどのように繋がっていったのでしょうか?
浅野:2011年の東日本大震災がきっかけで、防災関連の復興事業にも関わることになりました。復興庁の事業として、復興人材の育成や復興時の課題解決事例の教材化に取り組む中で、次第に災害対策や防災・非常食の課題に気づくようになりました。
その課題とは端的に言うと、人の感情が無視されていて、「○○をしなければならない」という押し付け的啓発ばかりであったことです。特に防災などどちらかというと非積極的な行動を要する件に関しては、意識変容より行動変容を促すことが重要だと思います……つまり、人は美味しいものや価格的に買いやすいものを買い、結果的に家に備蓄されるという考え方の方が、「備蓄してください」という意識啓発より重要だと感じました。
ちょうどその課題感を感じていた時に「食を中心とした宇宙を活用した防災ビジネス、防災ノウハウを活用した宇宙ビジネス」であるBOSAI SPACE FOOD PROJECT(以下、BSFP)との連携の話が立ち上がりました。BSFPはJAXAが、中長期計画の新しい施策として2018年より開始した、事業化までをスコープとした民間事業者等とのパートナーシップ型の新しい研究開発プログラムJ-SPARCのいちプロジェクトでした。この出会いをきっかけに宇宙関連事業に取り組むチャンスが生まれました。
宙畑:食を中心とした宇宙を活用した防災ビジネス、防災ノウハウを活用した宇宙ビジネス事業に取り組むということについて、事業として成り立つのかの不安はありませんでしたか?
浅野:私たちも「儲かる匂いがしないな」と思い、相当議論しました。そもそもの非常食の市場は年間約300億円の規模で、400億円の売上を超える「じゃがりこ」ブランドひとつにも満たない小さい市場です。
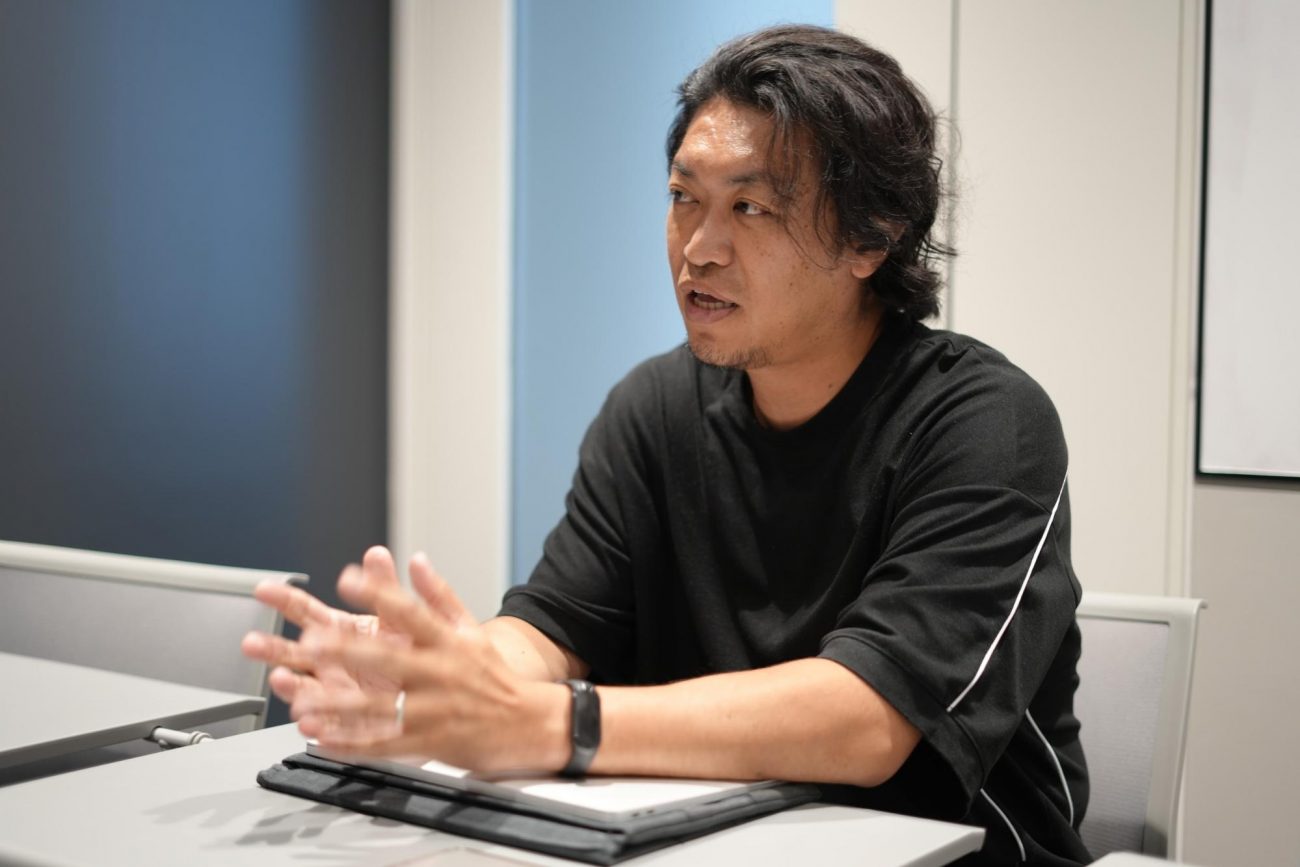
浅野:その理由は非常にシンプルで、基本的な人ひとりの1週間の食の回数は大体35(7日×朝昼晩の3回と間食の2回)回。この回数をスロットと私たちは呼んでいます。そしてこの35スロットのうち、自社の食品がどれだけのスロットをどれだけの頻度で埋められるかで食のマーケットにおいて見込まれる売上規模やシェアの感覚値が分かります。
この観点で見ると、非常食は地方自治体が大規模に購入したとしても、一度購入したら数年単位で更新されるだけですし、人々が日常的に買う食料と違って頻度が非常に低いんです。この購入と消費の頻度の低さが、市場がなかなか拡大しない原因だと感じました。
プロジェクトを進める中で「これは重要だな」と感じたのは、「ローリングストック」という考え方です。これは、普段の食事として非常食を利用しながら、自然と備蓄もできるというものです。「いざという時のために買わなきゃと思って買うのではなく、いつの間にか買っていました」という流れを作りたいと思っています。ただし、現在よくパンフレットや防災の日に近い小売店の棚でうたわれているような「ローリングストックをしましょう!」などの意識啓発では大きな行動変容にも至らないでしょう。
宙畑:宇宙食についても、購入をする方は少ないまだまだ小さい市場だと思うのですが、なぜ宇宙が関わるとビジネスチャンスがあると考えられたのでしょうか?
浅野:私たちは、単純に宇宙でも被災地でも使えるものをデュアルユースできる商品として見ているわけではありません。宇宙生活環境と被災地の環境の共通点をどう切り取るか、が重要と捉えています。クローズアップします。
例えば、狭い空間にずっといなければならない人や水が少なくて困っている人の気持ちなど、宇宙・被災地の類似した環境にいる人の感情に注目すると実は共通点がいっぱいあると気づきました。その観点で宇宙生活関連事業・防災関連事業の双方のイノベーションにつながるのであれば一緒にやりましょうとプロジェクトが進んでいきました。
「地上の潜在的な課題が宇宙では顕在化している」宇宙業界が面白いポイント①
宙畑:宇宙生活の環境の切り取りについて、もう少し詳しく教えてください。災害時だけではなく、どのような地上の環境との共通点が生まれるのでしょうか?。
浅野:例えば、狭い閉鎖環境でのストレスや栄養問題、健康維持などです。これらは宇宙という環境下で特に顕在化しやすい課題ですが、実は地上でも同様の問題が潜在的に存在しています。宇宙ビジネスの専門家がその問題を解決しようとしていますが、実際には地上でも、同じ問題にアプローチできるのではないかと感じました。
例えば、狭い空間にいるとストレスが溜まるのは当たり前ですし、年を取るとフレイル(虚弱化)の問題が出てくるのも自然なことですよね。ただ、これらの問題は、課題が十分に表面化されていないケースが多いため、解決に向けて十分なリソースや注目がまだ向けられていないことが多くあります。
ですが、宇宙の極限環境ではその課題が一気に顕在化するので、宇宙生活の実現には技術的な解決策がマストになります。このようにして、宇宙での解決策を地上の潜在的な問題にも応用できるとしたら、そこには大きなビジネスチャンスがあるんです。まだ誰も触れていないマーケットであれば、新たな市場を創造できる可能性があります。
宙畑:宇宙で顕在化する課題を地上のマーケットに活かせると感じた具体的な瞬間がありましたか?
浅野:2019年頃に宇宙の課題を地上にピボットするアイデアを図にしてまとめたことがありました。その時は、「宇宙で顕在化する課題を、地上の潜在的な課題に移行させる」というピボットの絵を描いたんですが、これが当時J-SPARCのプロデューサーでSPACE FOODSPHEREの理事でもある菊池優太さんに「こういう流れを作っていきたいね」と言われたことを覚えています。

浅野:宇宙で明確に浮かび上がる問題を見て、地上でまだ解決されていない分野を掘り起こせば、私たちにとっても、新たなビジネスチャンスが生まれるのではないかと思っています。
「様々な産業と研究の有識者が集う」宇宙業界が面白いポイント②
浅野:また、宇宙ビジネスの最大の魅力の一つは、様々な分野の有識者が集まってくる点です。たとえば、南極観測隊など様々な極地を経験されたエキスパートや、国の研究施設やアカデミアなどで災害の研究の第一線に携わっている方々、食品産業やフードテック業界のステイクホルダー、衣類や住環境に関わるプレイヤー、加えてもちろん宇宙関連産業に関わる方々といったように、宇宙に関連する場には多岐にわたる業界や研究分野の人たちが集まります。
こうした方々の話を聞くと、自分たちが宇宙生活や地上での日常生活、また有事における生活などの視点で捉えていたインサイトがさらに深まるんです。宇宙という極限環境の課題や知見を共有する中で、地上のビジネスにも役立つアイデアが得られるのが面白いですね。
宙畑:さまざまな知見が集まることの魅力はいつごろから気づかれたのでしょうか?
浅野:2019年頃から、宇宙という環境そのものだけでなく、宇宙に集まる多様な知識やスキルセットを活かして地上でビジネスを展開できるのではと考え始めました。宇宙に集まる研究者や技術者の知見は、地上事業におけるイノベーションを考える上で大変貴重なリソースです。
それに、宇宙というメッセージはある意味では非常に魅力的で、人々の注目を集めやすいという利点もあります。実際、宇宙を活用した地上のビジネス、つまり宇宙で得た知識を地上でのビジネスに応用することで、より多くの価値を生み出せると感じています。
繰り返しになりますが、宇宙という環境は特殊で、その厳しい条件下で直面する課題は、地上における我々の生活に通じる部分が多いんです。また、宇宙の独特な環境で研究を進めるために必要な知識や技術は、地上で活かすと新しいビジネスチャンスが生まれる可能性があります。これらの知識を組み合わせ、さまざまな分野の有識者と連携することで、新たな地上ビジネスを創出できると信じています。
Space Food Lab.の3つのチャレンジと事業化の光明
宙畑:現在、株式会社Space Food Lab.で進めているプロジェクトについて教えていただけますか?
浅野:Space Food Lab. (以下、SFL)は宇宙と地球の未来を食でつなぐ事業を展開しています。例えば、低コストでオフリッドな調理環境や持続可能な食生活環境などの創造など、いわゆる食品開発に留まらないより良い「食生活環境」の創造です。これらの取り組みを、精緻なブランディングとマーケティングを駆使し、宇宙を目指した地上ビジネスでの価値創出、宇宙をてこにした地球環境での事業イノベーション(Space Reverse Innovation)を通じた共創型事業を展開しています。
創立当初の2023年は、3つのプロジェクトに注力しました。まず「Space Stadium Food」では、スタジアムでの食体験を宇宙食の技術で向上させる試みを行い、「4/6プロジェクト」では、サプライチェーンの問題に着手し始めました。緊急時にも対応できるサプライチェーンを日常生活にも応用することで、持続可能な供給システムを構築しようとしています。
「Disaster Kitchen Assitance Team (DKAT)」というプロジェクトでは、災害時に役立つ調理システムやソフト面での運営・運用モデルを開発し、それを日常の生活にも適用する事業を立ち上げ、練り上げています。これらの取り組みを通じて、極限環境でも対応できる事業を地上の日常生活に転用し、儲かる事業として実現していこうとしています。

宙畑:地方自治体や企業との連携も進めているとのことですが、どのような形で実現しているのでしょうか?
浅野:特に地方自治体との連携を通じた地域の経済活性化に関心があります。たとえば、福岡県や久留米市と協力して、地域の食産業を含む地域の地場企業と食を中心とした宇宙の生活実現を結びつける試みを始めました。これは、宇宙というテーマが注目を集めやすく、地域振興のための新しい視点を提供できるからです。今後も九州各地域で自治体と協力し、宇宙を活用した地方創生プロジェクトを推進していきたいと考えています。
宙畑:Space Food Lab.の今後の展開はどのように考えていますか?
浅野:2024年は、宇宙ビジネスが地域経済にもたらす可能性への期待感が多くの地方で高まりを見せた一年でした。宇宙生活の「ゼロイチ」を実現する挑戦は、地域の循環型経済やリサイクル技術の強化といった課題解決の糸口を示し、未来志向の議論を活性化し、地球と宇宙双方で活用可能な取り組みが、地域資源の新たな活用法を模索するきっかけになっています。
久留米では、2024年末に地域食材や加工食品を通じて未来の食を議論する継続的な運営を想定したネットワーク型企画を実施する予定で、2050年の月面生活を見据えた地域発イノベーションの芽が育む予定です。この動きは、地域プレイヤーが久しく感じなかった「前向きな未来」を共有するきっかけともなると感じています。
また、一般的に想像する宇宙食とは異なりますが、素材メーカーとも連携を進めています。特にBtoB企業が宇宙関連の新しいビジネスに注目している状況です。考え方は宇宙食と同様で、宇宙環境のような極限状態で顕在化した課題を解決する素材の開発は、地上での潜在的な課題解決にも大いに役立つ可能性があります。BtoB企業がイノベーションを生み出す一つのきっかけとして宇宙があり、宇宙という新たな市場で素材の価値を高めることで、革新的な製品を生み出すことが期待できます。
このように、Space Food Laboでは、地上と宇宙を繋ぐ実用的なソリューションを提供することで、未来に向けた新しい生活インフラの一端を担いたいと考えています。
宇宙業界にはプレイヤーと案件組成できる人が少ない?農学での学びが活かされる浅野さんの強み
宙畑:宇宙業界でビジネスに参入される際に、懸念されていたことはありましたか?
浅野:ひとつは、宇宙ビジネスには、まだまだプレイヤーが少ないということです。利益を生み出すには、顧客がサービスに対してお金を支払う必要がありますが、そのためには共感や納得が求められます。宇宙に関心を持つ人は多いものの、実際にサービスやプロジェクトにお金を払ってくれる方はまだ限られています。
宙畑:実際に宇宙ビジネスの世界に入ってみて、どのような点に課題があると感じていますか?
浅野:一番の課題は、いわゆる「非宇宙」の方でも参画できる、したくなるようなビジネス案件を組成する人が少ないことです。宇宙には関心が集まりやすいですが、実際にそれを事業として進めるための案件組成力が不足していると感じています。
多くの人が集まって盛り上がっても、最終的には自分の職場に戻ってしまう。それでは、何も進展しません。宇宙関連で新しいプロジェクトを立ち上げ、実際に事業化するには、ビジネスとして確立できるスキームを作れる人が必要です。その部分が弱いと、せっかくのアイデアが形になる前に消えてしまうんです。
宙畑:案件を組成できる力はどのように身につけられたのでしょうか?
浅野:過去の事業会社での経験に加えて、産学連携や災害復興事業での経験が大きいですね。産学官民が協力し合う場に何度も携わる中で、それぞれの立場や利害関係が見えてくるようになりました。この経験を通して、どの関係者を巻き込み、「あの人とあの人をつなげば新しいプロジェクトが立ち上がる」といった「鼻」が利くようになったと思います。
宙畑:宇宙業界における案件組成の今後についてどうお考えですか?
浅野:宇宙業界には、まだまだ案件を組成できる人が必要です。私たちも受け皿としてプロジェクトを進めていますが、この業界全体で案件を形にする力が強化されるべきです。システム思考を持ち、どうやって人々の役割や目的をリンクさせるかを理解することが重要です。何をすればいいか明確な答えはありませんが、仕組みを見極め、それぞれの課題と目的をリンクさせることが案件組成において肝となります。案件組成力を高めていくことで、宇宙ビジネスがさらに広がる可能性は十分にあると思います。
宙畑:農学で学んだエコシステムの考え方が、案件組成にも影響を与えているのでしょうか?
浅野:そうですね。農学で学んだエコシステムの概念は、自分のシステム思考に大きく役立っています。複数の要素が影響し合うシステムの中で、どの部分に手を加えれば他の要素に波及効果があるか、という感覚は案件組成にも応用できます。宇宙業界も一つのエコシステムであり、異なるプレイヤーが協力し合いながら成り立っています。ですので、プレイヤー同士のつながりを意識し、それぞれがどの役割を果たすべきかを見極める力が、宇宙業界でも重要だと考えています。
浅野さんから宇宙業界への転職を考える方への一言
宙畑:最後に、宇宙業界に入ろうか迷っている方に向けて、メッセージをお願いします。
浅野:まず、迷っているならぜひこのタイミングで宇宙関連の企画、特に非宇宙プレイヤーも参加している機会に一度足を運んでみてほしいと思っています。いきなり「宇宙業界に入るぞ!」と大きな決断をする必要はないと思います。宇宙関連のビジネスに携わる人と一緒に何かを始めてみることが重要です。実際に肌を合わせ、一緒に活動してみると、宇宙関連ビジネスの感覚が掴めてきます。その感覚を得ることで、「こういうことをやってみたい」という想いが自然と湧いてくると入り口に立つことができるのではと思います。
逆に、プロボノのように外からスキルを提供する形だと、相手がどう活かすかに依存してしまい、自分の得意分野を十分に発揮できないこともあります。宇宙関連の業界でやりたいことがあるなら、まずは実際に関わりながら、自分の中で「これが自分の役割だ」と腑に落ちる瞬間を見つけることが大切です。宇宙ビジネスに関心がある人がいるなら、その人たちと一緒に何かを試しながら、この分野での可能性を実感してみてください。
編集部がグッと来たポイント
浅野さんのインタビューを通じて、「宇宙業界には、プレイヤーと案件を形にする力を持つ人が必要」という強いメッセージが感じられました。
また、P&Gの経営管理部門でマーケットを大きくする感覚を身につけられた浅野さんが宇宙という極限環境が地上の潜在的なマーケットを掘り起こすチャンスがあると感じられていることは、宇宙ビジネスの市場を大きくしたいと考えている宙畑編集部としては非常に心強く、ワクワクしました。
「Why Space」の連載は浅野さんで3人目のインタビューが完了しました。あらためて、宇宙業界は産業としては未熟な市場であるがゆえに、これから転職するだろうさまざまなキャリアを持つ人の多様な経験や発想が活かされる土壌が広がっていると感じました。浅野さんが語る「まずは一緒に動いてみることが大切」という言葉から、業界への参入は、堅苦しく考えるよりも、実際に関わりながら可能性を探る姿勢が大事だという学びを得ました。
「Why Space」では、引き続き、宇宙業界に新風を吹き込むビジネスパーソンの声をお届けしていきます。既存の枠に囚われない発想や、他業界での経験を活かして宇宙ビジネスに貢献したいと考える方々にとって、宇宙業界がいかに魅力的なフィールドであるかを伝えていきたいと思います。


